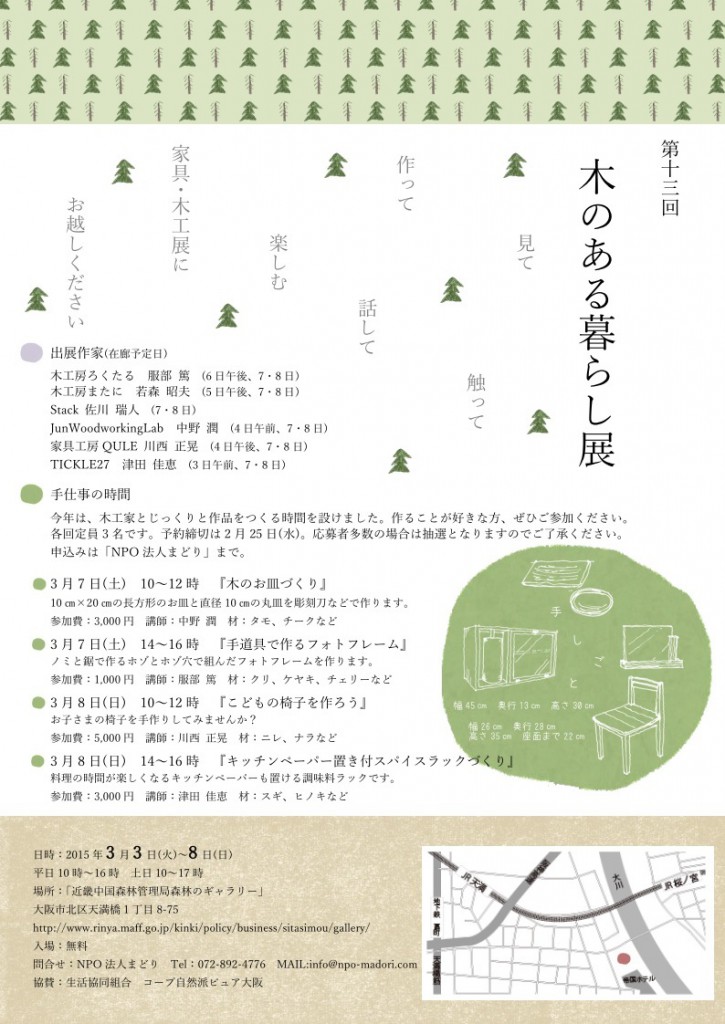補修の仕事も終り、仕掛の仕事を再開します。前に紹介したヒノキの薄板は、鉋で全体をめくってみると画像のような状態でした。ヤケが部分的に進んでいるのか、まだらになっています。それに木目がどうも私の好みではありません。制作意欲がかなり減退しました。
それではと、あらためて他の針葉樹の薄板を取り出して見ました。
計画変更というか、また新規に比較的大人しめの杉板を使って別のものを作ってみようかと思っています。
ところで、こうした針葉樹を削るのに画像の鉋がよく切れます。実は、この鉋は私の持っている鉋で一番新しく買ったものです。それでも、既に7年ほど前になります。三木の刃物市のあるイベントを見学している時に、たまたま隣り合った酔っぱらいのオヤジさんが、実は鉋鍛冶でした。それで、当然のように鉋の話になり、三木の他の鍛冶の鉋を愛用していると言うと、それならオレの鉋も使ってみろとなって、成り行きでその場で発注してしまいました。思い出したのですが、その時は普段の仕事に使う広葉樹用の鉋はもう間に合っているので、新規に打ってくれるのなら針葉樹用に「白」(白紙という炭素鋼)でお願いしたいと言いました。その鍛冶の爺さんは、オレは青が得意だから青にしてくれと言う事で、任せることにしました。
暫くして送ってきたのが画像の鉋です。カタログにもあるもので、体よく在庫処分をされたかと思ったりしましたが、あえて詮索はしないことにしました。頼みもしないのに、鉋の銘の裏に私の苗字が刻印されているのも余分なことで、私はこうした事が嫌いなのです。ただ、この鉋は、良い台にすげられていて、普通に研ぎやすくよく切れました。若干、刃持ちが悪いのは使い始めは仕方ないと言われています。でも、特にこれまで使い慣れたいくつかの鉋に代わるか、そのうちに入れるかという程でもない。それで、ほとんど使わずにいました。
最近、針葉樹の板を色々取り出して削ったりしていますが、ふとこの鉋の購入のいきさつを思い出しました。それで、試しにと使って見ました。普通に杉が削れます。杉のように一般に柔らかいと言われている材など削れて当たり前と思われるかもしれませんが、杉と地松、特に脂の多い肥松と言われる材は扱いにくいやっかいな材料になるのです。杉などは、広葉樹では普通に薄い屑が出て、そこそこきれいな削り面が作れるような鉋でも、粉しか出ない場合が多いのです。それで、少し刃を出し気味にすると、今度はむしり取るような厚い屑が出てしまう。
もう少し、ちゃんと鉋自体の調子を追い込んでから、また報告します。